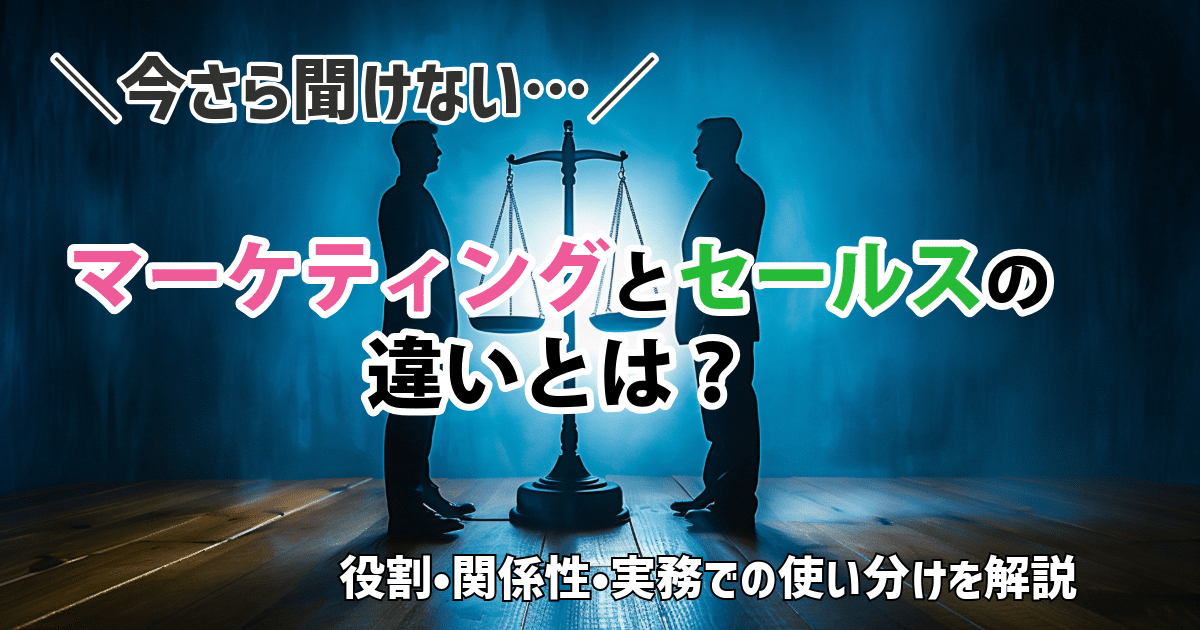
多くの企業において、マーケティングとセールスの役割混同や部門間の分断は、顧客体験の低下だけでなく、潜在的な売上機会の損失を引き起こす深刻な課題です。
本記事では、中小企業やBtoB企業の実情を踏まえ、マーケティングとセールスの明確な違いから、顧客の興味を育て、意思決定を支援する一貫した連携フローを解説します。
- マーケティングとセールスの本質的な役割と違い
- 部門間の分断が引き起こす課題とその解消方法
- データとツールを活用した効果的な連携戦略
- 自社の顧客離脱ポイントを見つける具体的なアプローチ
マーケティングとセールス 本質的な役割と目的
マーケティングとセールスは、企業の成長を牽引する二つの重要な機能です。
これらは異なる役割と目的を持ちますが、現代のビジネス環境において、その密接な連携こそが売上向上と顧客満足度を最大化する鍵となります。
特に中小企業やBtoB企業では、両者の役割が混同されたり、部門間で分断されたりすることで、顧客体験が途切れ、成果につながらないケースが多く見られます。
両者の本質的な違いを理解することが、連携強化の第一歩です。
| 項目 | マーケティング | セールス |
|---|---|---|
| 主な目的 | 認知度向上、見込み客育成、需要創出 | 商談化、成約、売上獲得 |
| 担当フェーズ | 潜在顧客の掘り起こし、興味喚起、育成 | 見込み客の商談、提案、契約締結 |
| アプローチ | 広範囲・間接的(Web、SNS、広告、イベント) | 個別・直接的(商談、訪問、電話、メール) |
| KPI | サイト訪問者数、リード数、MQL数、CPA、ROI | 商談数、成約率、売上高、LTV、CAC |
マーケティングは「売れる仕組み」を作り、セールスは「売る」ことに特化します。
この明確な違いを理解し、それぞれが自身の役割を十全に果たすことで、企業は持続的な成長を実現できるのです。
マーケティングの担当と目標
マーケティングとは、顧客のニーズを特定し、自社の製品やサービスの価値を伝え、見込み客を創出し、購買意欲を高めることで需要を創造する活動を指します。
市場調査やブランド認知度の向上を通じて、企業が安定して収益を上げるための土台を築きます。
具体的には、Webサイトでの情報発信やSNSを通じたコミュニケーション、検索エンジン広告やディスプレイ広告の運用、さらに展示会やオンラインイベントの企画と実行など多岐にわたります。
例えば、月間サイト訪問者数5万人、年間リード獲得数1,000件といった具体的な目標設定が可能です。
| 項目 | 役割 | 目標 |
|---|---|---|
| 担当 | 市場調査、製品企画、プロモーション | 認知度向上、ブランド価値向上 |
| 活動 | 情報発信、広告運用、リード創出と育成 | サイト訪問者数、リード数、MQL数の増加 |
マーケティング活動は、顧客との最初の接点を創出し、顧客の興味関心を育む役割を担います。
セールスの担当と目標
セールス(営業)は、マーケティングが見込み客へと育成した対象に対し、直接的に製品やサービスを提案し、商談を成立させて売上を確保する活動です。
顧客が抱える課題を深く理解し、その解決策として自社の商品やサービスを提示し、契約へとつなげます。
営業担当者は、見込み客との商談設定、製品やサービスのプレゼンテーション、価格交渉、そして契約締結までを一貫して担当します。
例えば、月間商談数10件中3件の成約、四半期5,000万円の売上達成といった目標が目指されます。
| 項目 | 役割 | 目標 |
|---|---|---|
| 担当 | 商談設定、提案、交渉 | 商談数増加、成約件数向上 |
| 活動 | 顧客への直接アプローチ、契約締結、フォロー | 売上高達成、LTV(顧客生涯価値)最大化 |
セールスは、企業に直接的な収益をもたらし、顧客との信頼関係を構築する最終的な役割を担います。
顧客獲得フェーズにおける役割
顧客獲得フェーズとは、潜在顧客が自社の製品やサービスを知り、購入を決定し、最終的に顧客となるまでの一連のプロセスを指します。
このフェーズでは、マーケティングとセールスが異なる段階でそれぞれの強みを発揮し、顧客を購買へと導きます。
マーケティングは、顧客がまだ製品やサービスの存在を知らない段階からアプローチを開始し、興味を持たせるための情報提供や見込み客の育成を行います。
その一方でセールスは、顧客が購入の検討段階に入った際に、直接的な対話を通じて意思決定を支援します。
両者がそれぞれの役割を果たすことで、顧客はスムーズな購買体験を得られます。
| フェーズ | マーケティングの役割 | セールスの役割 |
|---|---|---|
| 潜在顧客の認知と興味喚起 | 認知度向上、情報発信 | なし |
| リードジェネレーション | 見込み客創出(Webサイト、広告) | なし |
| リードナーチャリング | 育成(メール、コンテンツ) | インサイドセールスが連携し育成を支援 |
| 商談・提案 | 高品質リードの提供、資料作成サポート | 商談設定、提案、価格交渉 |
| 成約 | なし | 契約締結、売上確保 |
このように、顧客獲得の成功には、顧客が製品やサービスを認知してから購買に至るまでの各フェーズで、マーケティングとセールスが異なるアプローチで連携することが不可欠です。
アプローチの違い
マーケティングとセールスは、顧客へのアプローチの仕方において明確な違いがあります。
マーケティングが「広範囲かつ間接的」なアプローチで多くの潜在顧客に影響を及ぼすのに対し、セールスは「個別かつ直接的」なアプローチで特定の見込み客に深く関わります。
マーケティングはWebサイトやSNS、広告を通じて不特定多数のユーザーへ情報発信を行い、潜在的な興味関心を喚起します。
対してセールスは、商談や電話、メールを通じて個別の顧客と直接対話し、課題解決に向けた具体的な提案を行います。
例えば、マーケティングが実施したウェビナーで500名のリードを獲得した場合、セールスはそのリードの中から興味度の高い数名を絞り込み、個別の商談を設定するといった連携が考えられます。
| 項目 | マーケティングのアプローチ | セールスのアプローチ |
|---|---|---|
| ターゲット | 広範囲の潜在顧客、見込み客 | 特定の質の高い見込み客 |
| 手法 | Webサイト、SNS、ブログ、広告、ウェビナー、イベント | 直接訪問、電話、メール、オンライン商談 |
| 接点 | 不特定多数への情報発信、双方向コミュニケーション | 顧客との対話を通じた関係構築 |
アプローチの違いは、それぞれの目的達成のために最適化されており、この特性を理解することが、両部門の活動をより効果的にすることにつながります。
成果測定指標の違い
マーケティングとセールスは、それぞれの活動の成果を測るための指標(KPI:重要業績評価指標)が異なります。
これらのKPIは、各部門が自身の目標達成度を評価し、戦略を調整するための重要な手掛かりとなります。
マーケティングでは、サイトへの訪問者数、獲得したリードの数、営業がフォローすべき質の高いリード(MQL:Marketing Qualified Lead)の数、そして顧客獲得にかかったコスト(CPA:Cost Per Acquisition)や投資に対するリターン(ROI:Return On Investment)が主要なKPIです。
セールスでは、設定した商談数、商談から契約に至る成約率、実際に上がった売上高、さらに顧客との長期的な関係性から生まれる価値(LTV:Life Time Value)や顧客獲得にかかる費用(CAC:Customer Acquisition Cost)などが重視されます。
| 部門 | 主なKPI | 意味 |
|---|---|---|
| マーケティング | サイト訪問者数、リード数、MQL数、CPA(顧客獲得単価) | 見込み客の量と獲得効率を示す |
| セールス | 商談数、成約率、売上高、LTV(顧客生涯価値)、CAC(顧客獲得費用) | 最終的な売上への貢献度と顧客の価値を示す |
それぞれのKPIの違いを理解することで、各部門が企業の売上貢献に対してどのような役割を担い、どの段階で成果を出しているかを正確に評価できます。
これは、部門間の協力体制を築く上で重要な共通認識の基盤となります。
現代ビジネスにおけるマーケティングとセールスの関係
現代のビジネス環境において、マーケティングとセールスの関係は企業成長の重要な鍵を握っています。
顧客の購買プロセスが変化し、デジタル技術が進化する中、両部門の密接な連携による一貫した顧客体験の提供は、売上向上と顧客満足度最大化に不可欠な要素となります。
顧客購買プロセスの変化
インターネットの普及により、顧客は製品やサービスに関する情報を営業担当者に接触する前から、自ら詳細に収集できるようになりました。
企業からの情報だけでなく、Webサイト、ブログ、SNS、レビューサイトなどを通じて、比較検討を深めているのです。
この情報過多の時代では、顧客は自身のペースで購買意思を形成するため、企業の情報提供と関心育成の役割が購買プロセスの初期段階で重視されます。
結果として、マーケティング部門が購買プロセスのより早い段階から顧客との接点を持ち、信頼関係を築く必要性が高まっています。
顧客が多様なチャネルから情報を得るようになった現代では、企業は各接点での顧客体験を途切れさせないように設計しなければなりません。
部門間の分断が招く課題
多くの企業で、マーケティングとセールスがそれぞれ独立して活動する「サイロ化」という状態が見られます。
このような分断は、両部門が個別の目標を追求し、顧客情報や戦略が共有されないことで、複数の課題を生み出します。
サイロ化は、顧客へのメッセージに一貫性が欠け、見込み客の質が営業部門の期待値に届かない原因となります。
マーケティングが獲得したリードが営業部門でうまく活用されなかったり、顧客のニーズが営業からマーケティングへ適切にフィードバックされなかったりするケースがあります。
これらの問題は、リードの取りこぼしや売上機会の損失を招く大きな課題です。
マーケティングとセールスの分断は、最終的に顧客が期待する一貫した購買体験を提供できず、顧客満足度や長期的なロイヤルティの低下につながります。
連携による顧客体験の向上
マーケティングとセールスの連携強化は、顧客にとって一貫性のあるシームレスな購買体験を提供できる点が最も重要です。
顧客が企業の情報を初めて知り、興味を持ち、製品購入に至るまでの全ての段階で、両部門が協力して顧客をサポートします。
連携が進むことで、マーケティングは顧客の初期段階の疑問を解消し、関心を引きつけるコンテンツを提供できます。
そしてセールスは、マーケティングが育成した質の高い見込み客に対して、顧客の状況や課題に合わせた適切なタイミングで的確な提案を実施できます。
例えば、顧客が特定のサービスページを閲覧した情報を基に、営業担当者が関連する具体的な成功事例を商談で提示するなど、よりパーソナライズされたアプローチが可能となります。
このように部門が連携すれば、顧客は途切れることのない情報とサポートを受け、満足度の高い購買体験を得られます。
結果として、企業の売上向上と長期的な顧客ロイヤルティの確立に貢献します。
インサイドセールスの役割拡大
デジタル化の進展に伴い、顧客とのオンラインでの接点が増加しています。
この変化に対応し、インサイドセールスがマーケティングとフィールドセールスの間に位置し、両部門の連携を強化する重要な役割を担うようになりました。
電話、メール、Web会議システム、SNSなどを活用し、見込み客の育成や購買意思決定の促進をリモートで実行します。
インサイドセールスは、マーケティングが生成した見込み客に対し、非対面で継続的にコミュニケーションを取り、興味関心をさらに引き上げます。
また、顧客の潜在的なニーズや課題をヒアリングし、解決策を提示しながら、購入確度の高い「質の良い見込み客」を選別しフィールドセールスへ引き渡します。
これにより、フィールドセールスは訪問や商談準備に費やす時間を減らし、成約に集中することが可能になります。
インサイドセールスは、顧客の購買プロセス全体を通して途切れない体験を提供し、見込み客を効率的に商談へつなぐ重要な架け橋となります。
データとツールの連携活用
現代ビジネスにおいて、マーケティングとセールスの連携にはデータとツールの連携活用が不可欠な要素です。
顧客の行動履歴や興味関心などの多様な情報を一元的に管理し、共有できる環境を構築することで、両部門はより効果的に協力できます。
顧客管理システム(CRM)やマーケティングオートメーション(MA)ツールは、その中心となるツールです。
MAツールはWebサイトの訪問履歴、メールの開封状況、資料ダウンロードといった顧客の行動データを自動で収集し、CRMツールは営業活動の履歴や商談の進捗状況を管理します。
これらのツールが連携することで、例えばMAツールで見込み客の購買意欲が高まった際、その情報がリアルタイムでCRMに同期され、営業担当者は顧客の状態を正確に把握し、最適なタイミングでアプローチできるという具体的なメリットがあります。
データとツールを連携させることで、顧客へのアプローチはデータに基づいたパーソナライズが可能になり、マーケティングとセールスは顧客獲得から成約、そしてその後の関係維持までを一貫して効率的に進められます。
実務で成果につなげる連携戦略
現代ビジネスにおいて、マーケティングとセールスの分断は、多くの企業が抱える課題です。
この課題を解消し、両部門が協力して顧客を深く理解し、一貫した購買体験を提供することが、売上向上と顧客満足度を高める最重要課題であると私たちは考えます。
実務で成果を出すためには、具体的な連携戦略の構築が不可欠です。
この章では、実践的な連携戦略として、共通目標の設定から顧客旅程に沿ったフロー構築までを解説します。
共通目標と指標(KPI)の設定
KGI(Key Goal Indicator)とKPI(Key Performance Indicator)は、企業目標の達成度合いを測る重要な指標です。
マーケティングとセールスが連携する上で、まず両部門が共通のKGIを持ち、それを達成するためのKPIを設定することが肝要です。
例えば、共通のKGIを「年間売上総額1億円達成」とし、マーケティングは「月間MQL数100件」、セールスは「MQLからの商談化率30%」をKPIと定めます。
これにより、各部門が自身の役割を果たしつつ、全体目標への貢献を意識できます。
共通目標と指標を設けることで、各部門の役割が明確になり、連携による売上貢献度が測れるようになります。
| 指標 | マーケティングの役割 | セールスの役割 | 連携のベネフィット |
|---|---|---|---|
| MQL数 | 高品質なリードの安定供給 | 見込み客への効率的なアプローチ | 無駄のない商談機会の創出 |
| 商談成約率 | 購買意欲を高めるコンテンツ作成 | 顧客課題に合わせた提案と解決策提供 | 売上目標達成への確実な貢献 |
| 顧客満足度 | 価値ある情報提供とブランドイメージ向上 | 成約後のフォローアップと信頼関係維持 | LTV(顧客生涯価値)の最大化 |
共通目標の設定は、部門間の協調性を高め、目標達成への強い原動力となります。
リード定義と連携基準の明確化
MQL(Marketing Qualified Lead)はマーケティングが獲得・育成した見込み客、SQL(Sales Qualified Lead)はセールスがアプローチすべきと判断した見込み客を指します。
両部門でMQLとSQLの定義を明確にし、セールスに引き渡すリードの基準を統一することは、無駄な営業活動を減らし、成約率を高めるために不可欠です。
具体例として、資料ダウンロード後、特定ページを3回以上閲覧し、さらにメルマガを2回開封したリードを「MQL」と定義し、そこから個別相談フォームに連絡したリードを「SQL」とする、といった明確な基準を設ける必要があります。
これにより、セールスは質の高いリードに集中し、効率的な営業活動を展開できます。
明確なリード定義と連携基準は、見込み客の質を向上させ、売上への貢献度を高めます。
| 項目 | MQL(Marketing Qualified Lead)の例 | SQL(Sales Qualified Lead)の例 |
|---|---|---|
| 行動 | 特定のホワイトペーパーダウンロード、ウェビナー視聴 | 個別相談フォームへの入力、製品デモのリクエスト、見積もり依頼 |
| スコア | MAツールで「エンゲージメントスコア20点以上」 | 営業との面談を希望する旨を明確に表明 |
| 興味関心度 | 課題意識はあるものの、具体的な検討段階ではない | 自社製品・サービスへの導入意欲が高い |
| 次のアクション | さらなる情報提供、ナーチャリングメール | 営業による初回アプローチ(インサイドセールス) |
明確なリード定義は、無駄な営業リソースの削減と、成約率の向上に直結する要素です。
定期的な情報共有と対話
部門間の情報共有不足は、顧客体験の分断と機会損失を招きます。
マーケティングとセールスが「シームレスな連携」を実現するためには、定期的な情報共有と活発な対話が欠かせません。
例えば、月に一度の合同ミーティングを設けて、マーケティングは最新のキャンペーン効果を報告し、セールスは顧客からのフィードバックや市場の生の声を共有します。
実際にこのような情報共有を徹底した結果、顧客離脱率を10%削減できた事例もあります。
顧客の反応や市場の動向をリアルタイムで共有することで、両部門は互いの活動を理解し、より効果的な戦略を策定できます。
情報共有を通じて、マーケティングとセールスは共通認識を持ち、連携を強化できます。
| 目的 | マーケティングからの情報共有 | セールスからの情報共有 | 連携によって生まれる価値 |
|---|---|---|---|
| 市場理解の深化 | 最新の市場トレンド、競合情報 | 顧客のリアルな課題、商談状況 | 戦略の精度向上 |
| コンテンツ改善 | 閲覧率の高い記事、効果的な広告 | 顧客が求める情報、質問が多いポイント | リード質の着実な向上 |
| 営業戦略の最適化 | 高品質リードの特性、購買意欲の傾向 | リードの課題感、アプローチ後の反応 | 成約率の持続的な改善 |
定期的な情報共有は、両部門の相互理解を深め、戦略と戦術の精度を向上させる不可欠な活動です。
共同コンテンツ開発と活用
コンテンツは顧客の購買プロセスを左右する重要な接点です。
マーケティングとセールスが共同でコンテンツを開発し活用することで、顧客へのメッセージの一貫性を保ち、購買意欲を高められます。
具体例として、セールスが商談で頻繁に聞かれる質問や顧客の懸念点をマーケティングにフィードバックします。
マーケティングはその情報をもとに、顧客の疑問を解消するブログ記事やFAQコンテンツを優先的に作成できます。
このような連携により、作成したコンテンツのエンゲージメント率が20%向上したケースもあります。
これにより、顧客は常に最適な情報に触れることができ、両部門は効率的にリードを育成できます。
共同コンテンツ開発は、顧客の信頼を深め、購買行動を促進します。
| コンテンツ例 | 開発の関与部門 | 主な活用場面 | ベネフィット |
|---|---|---|---|
| 事例集(導入企業の声) | セールス、マーケティング | 商談時、Webサイト | 顧客への信頼感と共感提供 |
| 製品・サービス比較表 | マーケティング、セールス | リードナーチャリング、商談時 | 意思決定支援、競合優位性の明確化 |
| 課題解決ガイド | マーケティング | リードジェネレーション、リードナーチャリング | 潜在顧客の掘り起こし、興味の育成促進 |
共同コンテンツ開発は、顧客の購買意欲を高め、両部門が同じ方向性で価値提供を強化する基盤となります。
顧客旅程に沿った連携フロー構築
顧客旅程(カスタマージャーニー)とは、顧客が製品やサービスを認知し、検討し、購入に至るまでの一連のプロセスを指します。
顧客旅程全体を通して一貫した体験を提供することは極めて重要です。
マーケティングとセールスは、それぞれの顧客接点において最適な役割を担う連携フローを構築します。
具体的な例として、MAツールでWebサイトの行動履歴やメール開封率が高いリードを検知した際、自動的にCRMツールへ情報を連携し、インサイドセールスに通知します。
これにより、インサイドセールスは顧客の興味が最も高まったタイミングでアプローチでき、リードの商談化率が15%向上したという実績があります。
このように各フェーズでの連携を仕組み化することで、顧客の購買意欲を途切れさせず、スムーズな移行を促します。
顧客旅程に沿った連携フローは、各部門の役割を明確にし、顧客体験を最適化します。
| 顧客旅程フェーズ | マーケティングの役割 | セールスの役割(インサイド/フィールド) | 連携アクション |
|---|---|---|---|
| 認知 | ブログ記事、広告による情報発信 | (関与なし) | 潜在顧客の掘り起こし、ブランド認知促進 |
| 興味関心 | ホワイトペーパー、ウェビナーで育成 | インサイドセールスが課題ヒアリング | ナーチャリングから営業へのスムーズな引き渡し |
| 検討 | 事例集、製品比較情報提供 | フィールドセールスが個別提案、デモ | 顧客ニーズへの的確な対応、購入意思決定支援 |
| 購入 | (関与なし) | フィールドセールスが契約締結 | 成約情報の共有、顧客情報の蓄積 |
顧客旅程に沿った連携フローは、顧客に一貫した体験を提供し、購入までの障壁を取り除くことで、成約率を最大化する効果的な戦略です。
実践的なマーケティング・セールス連携を築く Practical Marketing
マーケティングとセールスの連携は、単なる業務効率化に留まらず、顧客の体験を途切れさせないための重要な戦略であると私は考えています。
分断された活動は顧客の信頼を損ない、結果として機会損失につながります。
この連携を実務レベルで機能させるためには、現状把握から始まり、具体的な仕組みを構築し、外部の専門家の知見を活用することも有効な手段となります。
自社の顧客離脱ポイントを見つける
マーケティングとセールスの連携を強化するためには、まず自社の顧客がどこで購買プロセスから離脱しているのかを明確に特定する作業が重要です。
多くのBtoB企業では、見込み客が獲得されてもセールスに引き継がれるまでに時間がかかり、約30%のリードがこの段階で関心を失ってしまうケースも見てきました。
また、マーケティングが育成したリードが、セールスで再度ヒアリングされることになり、顧客が煩わしさを感じてしまう場面も少なくありません。
具体的な分析項目は以下の通りです。
- Webサイトの訪問者数からリードへの転換率
- リードからMQL(Marketing Qualified Lead)への育成率
- MQLからSQL(Sales Qualified Lead)への引き渡し率
- SQLから商談への移行率
- 商談からの成約率
これらの離脱ポイントを特定することで、マーケティングとセールスが連携して改善すべき具体的な課題が見えてきます。
戦略と現場をつなぐ仕組みづくり
顧客離脱ポイントが明確になったら、次に必要なのは戦略レベルで描いた連携を現場で実行できる仕組みを構築することです。
多くの企業では、部門間の目標や評価指標が異なり、これが連携を阻害する要因となります。
共通のKPI(重要業績評価指標)を設定し、例えば「月間MQL数100件、そのうちSQL転換率30%達成」のように具体的な目標を共有することで、両部門が協力して動く土台ができます。
効果的な仕組みづくりのステップは以下の通りです。
- 共通のKPIと目標を設定
- リードの定義と引き渡し基準を明確化
- 定期的な情報共有ミーティングの実施
- 共通のCRM/MAツールの導入と活用
- 顧客情報の相互フィードバック体制の確立
このような仕組みを導入することで、マーケティングが創出した価値をセールスが確実に成果へとつなげ、顧客に一貫した体験を提供できます。
Practical Marketingへの相談
マーケティングとセールスの連携強化は、多くの企業にとって喫緊の課題であり、その実現には専門的な知見や客観的な視点が必要になるケースも存在します。
私たちのPractical Marketing コンサルティングサービスでは、貴社の現状に合わせた実践的な連携戦略の立案から実行までを一貫してサポートしています。
これまで20社以上の中小企業やBtoB企業で、分断されたマーケティングとセールスを統合し、売上向上と顧客満足度向上を実現してきました。
特に、リード獲得から成約までの期間を平均1.5ヶ月短縮し、成約率を10%改善した事例も持ち合わせています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 強み | 中小・BtoB企業の特有課題に対応、実践的な施策立案 |
| サポート範囲 | 顧客離脱ポイント特定、連携フロー設計、KPI設定、ツール導入支援 |
| 期待効果 | リード獲得数の増加、成約率の向上、顧客満足度の改善、LTV最大化 |
| サービス形態 | 個別コンサルティング、ワークショップ、伴走型支援 |
貴社のマーケティングとセールスの連携を次のレベルへ引き上げ、持続的な成長を実現するためにも、ぜひ一度Practical Marketing コンサルティングサービスにご相談ください。
まとめ
「マーケティング」と「セールス」は異なる役割を持つものの、両者の混同や分断は、顧客体験を途切れさせ、結果として売上機会の損失を招く大きな課題です。
この記事では、中小企業やBtoB企業が直面するこの課題に対し、連携を強化し、顧客が認知から購入に至るまで一貫したスムーズな体験を提供する重要性を解説しました。
- マーケティングとセールスは「売れる仕組み作り」と「売る」という本質的な違いがあること
- 顧客購買プロセスの変化に対応するため、部門間の分断を解消し、連携による顧客体験の向上が必須であること
- 共通目標、リード定義、情報共有、共同コンテンツ開発などを通じた実践的な連携戦略が売上を伸ばすこと
- 自社の顧客離脱ポイントを特定し、戦略と現場をつなぐ仕組みを構築すること
貴社が売上向上と顧客満足度最大化を目指すのであれば、まずは自社の顧客がどこで離脱しているかを見つけることから始めてください。
そして、マーケティングとセールスの連携接点を設計し直し、リード獲得から成約までの一貫した流れを構築することが肝心です。
戦略と現場をつなぐ仕組みづくりに関心がある場合は、ぜひPractical Marketingまでご相談ください。
貴社の課題や目標に合わせて、最適なマーケティング戦略と実行支援をご提案します。
まずはお気軽にご相談ください。

